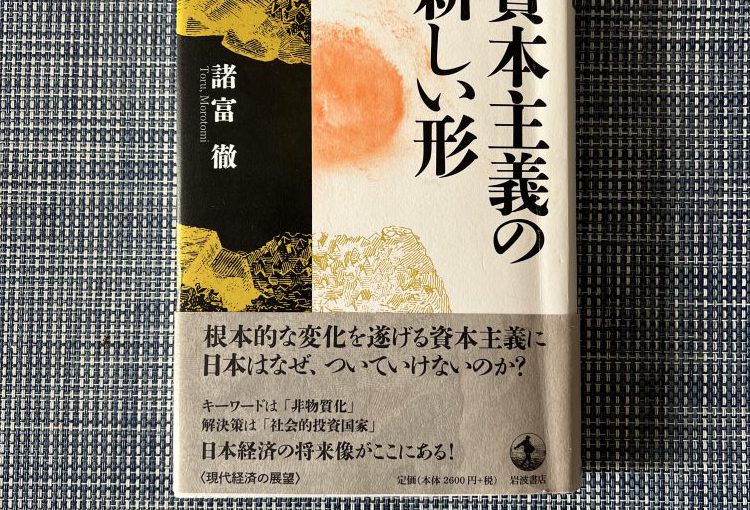第3章で初めて著者の環境経済学者としての顔が現れる感がある。すなわち、近年における「資本主義の非物質化的転回」は同時に経済の「脱炭素化」の動きに連動しており、この潮流においても、日本は他の欧米先進国に遅れを取って来ている。そして、この事が同時に我が国の「失われた30年」と符節を合わせており、我が国における「脱炭素化」への理解と取組みの遅れが同時にこの時期の日本経済の停滞の一つの原因となって来たのではないかと言う議論が展開されている。
この議論はやや唐突な感があり、当初は余りに我田引水に過ぎるのではないか、との感想も持ったが、考えてみれば、従来の有形資産の資本財による物質的商品の生産とその消費が多くの炭素の生成・排出を伴うのに対し、インターネット等の電子空間でデジタル情報等の無形資産を扱い、それらの集積、加工、伝達等で大きな付加価値を生み出す「非物質化的」経済は、確かに炭素の生成を伴わない面が大きい。そのような意味では現代の「資本主義の非物質化的転回」が同時に「脱炭素化」と連動するという議論は成り立つのかもしれないと思えて来た。
目次構成に従えば、この第3章の最初の節<1 日本企業の国際競争力低下>の中の小節<1. 象徴としての電機産業の凋落>では、まず近年の日本経済の話題として常に取り上げられるかつての我が国の花形企業の凋落ぶりが指摘されている。確かに1990年代までのソニーやパナソニックの圧倒的な世界的存在感は、近年の話題となったシャープの台湾企業による買収やアップルや中韓の企業の躍進の前に見る影もない携帯電話市場での失速など、その凋落ぶりは目を覆うばかりである。
<2.労働生産性と収益率の低下>において、著者は、この日本の産業競争力の低下の要因に関して、著者独自の視点から、「1980年代以降顕著になってきた資本主義の非物質主義的転回にうまく適応できなかったからではないか」という仮説を提示している。
そして、その競争力の低下の状況を労働生産性(付加価値総額/就業者数)と資産収益率(ROA 収益/総資産)の推移の国際比較に着目して検討している。
労働生産性については、1990年代には世界の首位だったのが、2000年以降順位を下げ2016年には15位まで低落し、時を追うごとに日本の製造業の労働生産性は悪化している。
また資産収益率についても、バブル崩壊以降のほぼ全期間にわたって日本の製造業のROAは米・独の製造業を下回っており、日本企業の低収益性が確認できると言う。
<3. 設備投資の低迷>においては、2.の収益性低下の背景要因を探る中で、日本の製造業において設備投資が長年にわたり抑制され、設備の更新が遅れ、設備の老朽化によって企業の収益性が低下したのではないか、との推測が述べられている。その背景として、まず第一に日本の人口の減少と市場縮小の予測から生産能力の改善投資や増強投資に経営者が慎重になったこと、第二に経営者は2000年代以降、株主からの強い配当要求の圧力により短期利益の拡大を図ろうとしたこと、第三にそのような株主への高水準の配当支払いの後の手元資金(内部留保)を生産設備と労働者に再投資するより現預金として企業内部に積み上げる方向に動いた、というような要因を取り上げている。
では、なぜこの時期、企業が積極的な投資を行わなかったのか、という点について<4. なぜ無形資産投資の重要性を理解できなかったのか>において著者の見解が述べられている。この時期、経営者は市場の成長拡大が期待できず、投資機会が少ないという姿勢が目立ったが、著者の考えでは、決して投資機会が失われていたわけではなく、日本の経営者の多くが従来型の「ものづくり」的な発想に執着し、資本主義の非物質化に伴う「投資の非物質化」への発想転換ができなかったためではないかと考えている。GAFA等の新しいビジネスモデルの企業が次々に登場し「経済の非物質化」という変化の重要性を理解し、それに対応した事業構造の転換を進めたアメリカではこのような新たな「非物質的投資」の重要性を理解した経営の転換が1990年代から始まり2000年代以降加速していった、とする。
このような無形資産への投資とは、コラードらによれば1)「情報化資産」への投資、2)「革新的資産」への投資、3)「経済的競争能力」への投資に分類される。そして、これらの新しいタイプの投資は、コラードらによるアメリカにおける研究では、1970年代以降一貫して増大し、1990年代には有形資産投資を上回り、以後ますます重要性が高まっている。この無形資産投資は情報通信技術(ICT)投資と合わせてデジタル化を推進し、サービス産業と製造業の融合による新しい産業を成長させてきた。この無形資産投資による成長促進効果は、製造業の物的投資による成長促進効果を上回り、このような成長率のより大きな無形資産集約産業の拡大による産業構造の転換が経済全体の成長を促すことが実証的に明らかにされている。
ところが、宮川らによる研究によれば、日本企業はこのような無形資産投資への転換に完全に立ち遅れた。このため生産性も伸びず、成長率の低迷からも脱却できないのだと言う。
次に、<5.何のためのICT投資か>において、日本においては、ICT投資を中心にした無形資産投資が高収益を稼ぎだす新しいビジネスモデルを展開する手段であることに長年気づかず、単に社内業務効率化の手段としてしか理解されてこなかった。日本の経営者はIT投資の重要性についての理解度が低く、IT投資に積極的ではなく、しかもこの投資を企業の売り上げを増やす方向ではなく、コスト削減や人員削減の手段として考える傾向が強く、このためIT投資が積極的な企業の成長につながらず、それが日本企業の国際的競争力の低下につながったとする。
それは私自身の経験からも切実に感じたことであるが、新しいIT技術が生まれ普及していく中で、日本の組織はいかにも消極的に渋々対応するという姿勢で、この革新的な新技術をどう活用し、我々の活動をどう展開していくかという積極性が感じられないことが多かったと思う。
さて、第2節<資本主義の非物質的転回としての「脱炭素化」>は著者の環境経済学者としての主張が明確に現れる部分である。この論理展開は、一瞬、著者のキャリアからの我田引水かと思われたが、考えてみれば、投資、生産、消費の非物質化はモノの生産・消費を中心とする物質的経済に対して「脱炭素」的であるのは確かである。そして著者の考えによれば、我が国のIT投資への理解不足と消極的対応と「脱炭素化」への対応とは共通して相似形を描いているとする。
この節の最初の小節<1.資本主義の死命を制する脱酸素化>では、「非物質化」と「脱炭素化」とは全く別の課題に見えて実は多くの点で重なり合っている、と説明する。すなわち脱炭素化を図りつつ成長するためには、エネルギー集約型の産業構造からより知識集約的な産業構造に転換し「情報化」「デジタル化」「無形資産化」「サービス化」の新しいビジネスモデルに転換する必要があるからである。従来、厳しい環境政策は企業の国際競争力を削ぎ、成長にマイナスとされ逆に急速な経済成長は環境を犠牲にする傾向があるとされてきた。しかし今後は両者はもはや相対立する関係ではなく、むしろ相互補完的、相互促進的な関係となっていくとする。そして「脱炭素化」を資本主義の非物質化的転回の一環として位置づけることを提唱する。
そして、<2.新しい投資機会としての脱炭素化>では、上のような捉え方から、脱炭素化をむしろ非物質化的転回を遂げる新しい資本主義の中での新しい投資機会と考えて、積極的、前向きな取組みをすべきではないかと説く。なぜなら「脱炭素化」をめざすことで事業の「非物質化」が進み、無形資産への投資が増え、それは「高付加価値」のプロセスとなるからであるとする。
ところが<3.脱炭素化を前に立ち止まる日本>の中で説明されているように、このような流れの中で、日本企業は脱炭素化を新しいビジネスチャンスとしてよりもコスト上昇要因、競争疎外要因として捉える傾向が強く、IT投資に対する態度と同じく、消極的な渋々の対応になる傾向が強かったという。
これに対し著者は4.で<脱炭素化と経済成長は両立する>と主張する。この小節の中で、著者は「デカップリング」と「炭素生産性」という興味深い二つの概念で、この主張を説明しようとしている。高度経済成長期、どの国においても、GDPの成長に比例的あるいはそれ以上の比率でエネルギー消費量やCO2排出量は増加していた。しかし、1990年代初頭に始まった温暖化対策の結果、2000年以降経済が成長してもCO2排出量は逆に減少する現象が見られる国が現れ、これを「デカップリング」(経済成長とCO2排出量の伸びとの分離)と称するようになった。ただこの現象の現れ方は先進各国でも相違があり、スウェーデン・フランスでは明確であったが、日本では依然として成長率とCO2排出量の伸びが比例的であり、他方、カナダ・イギリス・ドイツなどでは、2000年以降にこの現象が現れるようになった。
しかもデカップリング傾向が明確な国の方が明らかに成長率が高い傾向が見られ、「温暖化対策は経済成長を妨げる」という言説を否定する現実のデータになっていると言う。そしてデカップリングできていない日本は、CO2の排出削減もできず経済成長率も低い「後進国」に転落しつつあると言う。
さらにもう一つの興味深い概念である「炭素生産性」の国際比較でも、同じ現象が証明できると言う。ここで提示される「炭素生産性」は私には初めて接する概念であったが、一単位のCO2排出量あたりの付加価値(GDP)を示している。そしてこの炭素生産性の国際比較を見ると、日本は1995年ではスイスに次ぐ第2位であったのに、その後他国に抜き去られ、2015年にはアメリカに次ぐ最下位水準にまで低落していると言う。(ただ著者の主張では最も「非物質的転回」への対応に成功してきたはずのアメリカが「炭素生産性」において最下位になっているのは矛盾する気はするが)。結論的に言えば、欧州諸国は「製造業のデジタル化/サービス産業化」を進め、より高付加価値分野に事業領域を移してCO2削減してきたのに、日本企業はこれまで「ものづくり」の強みにこだわり過ぎたことにより、資本主義の非物質的転回への対応が遅れ、同時に脱炭素化でも遅れたという事になる。
次に<4.脱炭素化と産業構造の転換>においては各企業での取組みから各業種ごとの炭素生産性に目を転じ、各業種によって炭素生産性に大きな違いがあり、より炭素生産性が高く、成長性が高い業種を中心にした産業構造全体の転換を目指す必要があること、GDPの量だけではなくその質が問われる時代になっていると説かれている。そして「付加価値」という国民経済的な評価視点に加え、「総資産利益率」という投資家的な評価視点から見る時、一般的には、製造業全体平均よりも炭素生産性の低い業種は(化学工業を除いて)いずれも利益率が低いという事実が示されている。そして日本経済が脱炭素を図りつつ経済成長を達成するには炭素生産性がより高く同時に総資産営業利益率の高い方向へ産業構造をシフトさせる必要があると主張している。
この節の最後には<6.産業政策上の政策手段としての「カーボンプライシング」>について触れられている。この「カーボンプライシング」という用語も私には初めて接するものであったが、これは、環境税や排出量取引制度のように、CO2の排出に対して価格づけを行い、CO2の排出が地球環境に与える負の影響(「外部不経済」)を反映した対価を排出者に負担させる仕組みであると言う。そして北欧諸国が1990年代初頭に炭素税を導入して以来30年のデータから、カーボンプライシングが少なくとも経済成長を阻害することはなく、むしろ産業構造転換を促し、それを採用した国の経済成長を促進した可能性すら考えられるという仮説を提示している。
つまりカーボンプライシングは欧州企業の事業構造転換を後押しし、より高付加価値の事業領域へと促し、その結果、欧州企業のデカップリングを誘導した可能性があると言うのである。
そして、第3節<「製造業のサービス産業化」と日本の製造業の将来展望>において、上記のような産業構造転換をもたらした中核的要素として「製造業のサービス産業化」についての分析が行われている。
その最初の小節<1. 製造業のサービス産業化とは何か>においての説明によれば、一国全体としても個別企業としても成長と脱炭素化の同時達成を成し遂げた鍵は「製造業のサービス産業化」であり、これが21世紀における「資本主義の新しい形」の重要な一面であると言う。「サービス化」そのものは、以前から言われている産業発展段階において、第一次産業から第二次産業へ、さらに第三次産業へと主軸産業が移行するというペトラ=クラークの法則と呼ばれる現象を指すものである。これに対し、「製造業のサービス産業化」として近年注目されているのはこうした産業間の重点移行だけでなく、第二次産業である製造業そのものがサービス産業としての色彩を強めている現象を指す。それは製造業がサービス産業と融合することで両者の垣根が溶解していく劇的な変化が生じているという点で注目されていると言う。これは製造業が単に物的生産を行うだけではなく、製造業が同時にサービスから収益を上げることを目的としてサービスを購入・生産・販売し収益の源泉をより強くサービスに依存する傾向を意味する。この「物的生産と結合したサービス」が製造業の提供するサービスの強みになっていくと言う。歴史的に見れば、物的生産そのものが生み出す付加価値は低下する傾向にあり、製造業が、より大きな付加価値を生み出すサービス業に重点を移していくのは望ましいことである。そしてこのようにして「サービス提供のために物的生産を行う」というビジネススタイルへの変化が起きるその過程を「製造業のサービス産業化」と定義している。
次の小節<2.製造業のサービス産業化と第四次産業革命/産業のデジタル化>では、重なり合う部分もあるが製造業のサービス産業化と第四次産業革命(産業のデジタル化)とは区別して考えるべきであるとされている。第四次産業革命はデジタル技術によって工業製品の製造過程の効率化を図り生産性を向上させる事であり、著者によれば、それは視点が生産過程に偏り過ぎており、生産者が消費者(顧客)との接点をどう広げていくか、という視点が不十分であると言う。製造業のサービス産業化においては、顧客との接点がきわめて重要なポイントであり、カナダの経営コンサルタントのマッキナニーの指摘をもとに、できる限り多くの顧客情報を自社のオペレーションに組み込み、その顧客情報をいかに素早くキャッシュ化できるか、という目的のためにIT技術を活用することが重要である、とされる。そして、過去20年間日本企業は生産者の論理で「良い製品を作れば売れる」という信念で行動し、市場の側の需要側(消費者側)をマネージすることに失敗し、シェアを失い、国際競争に敗れ続け、その結果が『失われた20年』になった。そして<3.製造業のサービス産業化はどのように進行したのか>では、そのような現象が進行した主要因の一つは物的消費の飽和であり、ゴードンが言うように、生活の質を物的な意味で根本的に改善するようなインフラや製品・サービスがすでに行き渡ってしまったという状況が大きな要因であるとする。もう一つの主要因は製造業者がサービス化を進める方が収益性が高まるという事情にあったとする。この点について、日本では、1990年代から、逆に「ものづくり」という言葉が神聖化され、それが過度に生産者中心主義的な発想を強め消費者起点の発想に切り替える妨げになったのではないか、と言う。
<4. 「サービスで稼ぐ」製造業>では、以上で説明されたような「製造業とサービス業の融合」が現実にどのような形で進行しているのかについて、自動車業界、航空機業界、農業、エネルギー分野を例に詳細に説明されている。そして、このような取組みについての対応が遅れ気味の日本においての先進的実例として、建機メーカーの小松製作所の取り組みが紹介されている。