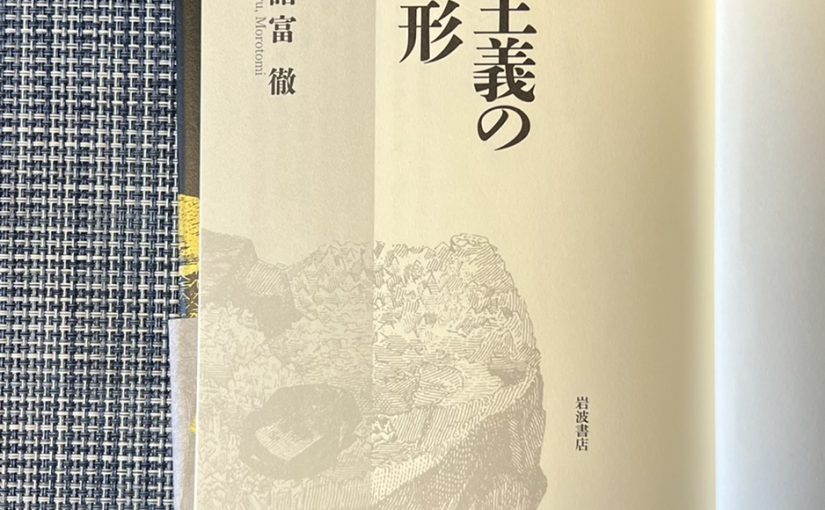諸富 徹 著『資本主義の新しい形』研究レポート(2) 11/13 ‘22
兵庫県立大学経済学部大学院 松賀正考
第2章は、第1章で予告されている通り「資本主義の新しい形」をとらえるために資本主主義の非物質化現象についての議論が詳細に展開されている。
まず、<1. 資本主義の「非物質的転回」とは何か?>において、このような現象に注目した先駆的論議を取り上げている。そのような先駆けとしては、既に1960年代に現れたマッハルプの「知識産業論」があり、ここでは「知識」という言葉を幅広く定義し、それを生産・活用している産業を特定し、そのような知識の生み出す付加価値が1958年時点で、アメリカGDPの約30%も占めており、今後その比率は時とともに増大するだろうとした。
次に、1970年代に入り、ダニエル・ベルが『脱工業社会の到来』(1973)でアメリカ経済の構造がモノの生産を中心とする工業社会から非物質的な価値を提供するサービス経済へ移行しつつあることを統計的に確認した。
さらに1990年代にピーター・ドラッカーが『ポスト資本主義社会』(1993)の中で、ポスト資本主義社会でもっとも重要な経済的資源はもはや資本や労働ではなく、知識社会においては、経済的価値は知識をベースとした生産性の向上とイノベーションによって生み出される、とした。
このドラッカーの影響を受けて、日本では神野直彦はこのような大きな産業の変革に対して、生産現場においては、工業社会時代の均一性、正確性、規律から、知識社会時代における多様性、柔軟性、創造性が求められる状況になり、工業社会対応型から知識社会対応型へ変化する必要があると主張した。
このような先駆的議論では、現代の資本主義社会の変化を「知識」という非物質的要素で説明して来たが、このような生産面での資本と労働のあり方の変化だけではなく、消費面からの変化も生じており、この生産・消費両面の変化を統合的に捉えるために、「非物質化」という概念を元に分析する方がより有用であると主張している。ただし、この非物質化は単純に物的なものが非物質的なものに置き換えられ物的なものが無くなると言う意味ではない。「非物質化」とは、物質的なものに非物質的要素が付加されたり、製造業がサービス業と融合するなどして、「物的なもの」が「非物質的なもの」によって新たな価値を持つことで非物質的要素の重要性が機能面でも経済価値の面でも格段に大きくなることを意味し、これを「非物質主義的転回」としている。そしてこの「非物質主義的転回」は資本と投資、労働、消費の全ての面に現れているとする。
資本の非物質化について言えば、かつてのように資本の中心は工場の機械設備等ではなく、生産にとって重要なのは新しい製品を生み出す研究開発や新しいアイデアのイノベーションを引き出す環境整備や経営戦略の策定、全世界に広がるネットワークの構築とそれらを支える制度構築と「人的資本」への投資である。これらはいずれも形のない「無形資産(intangibles)」であり、その厚みと質の高さが企業の競争優位につながる。企業が生産に用いる資本が工場設備などの物的なものから人的資本や無形資産など非物資的なものへ移行すれば、投資も非物質化することになる。
資本や投資のみではなく、労働においても、かつての工業化時代には製品を加工し、組み立てて物的価値を創出するための肉体労働が中心だったが、肉体労働の相対的重要性は低下していき、財・サービスに「非物質的価値」を付与できる労働の形が求められる。それは知的、コミュニケーション的、関係的、情動的な活動が労働の中心になる。
そして現代経済の「非物質的転回」は生産面だけではなく消費面にも現れており、むしろ「消費の非物質化」が起点となり、需要構造を変え、製品・サービスのあり方に影響を与えて来ているとも言える。その背景には、人々が物的欲求よりも非物質的欲求を満たすことにより関心を持つような価値観の変化がある。世界的に大規模な「世界価値観調査」を分析したロバート・イングルハートによれば、「近代社会」では経済成長と所得上昇が何より優先されるのに対し「ポスト近代社会」では生活の質や主観的幸福に重点が移っている。また人々の価値体系が「物質主義的価値」から「非物質主義的価値」に移行しつつある、という。だから生産者は人々の非物質主義的な価値要求を満たすことのできる製品・サービスを生み出さなければ利潤を獲得できず、市場競争で生き残れなくなっていき、そのため消費のあり方の変化が生産のあり方の変革につながっている。
次の<2. 経済学における「非物質主義的転回」>は、ほとんど純粋な『経済学史』的解説であり、理論的、概念的な論議で実証的分析は無い。マンキューとローマーによる1992年の論文で提唱された Y=F(K,H,AL) という経済成長に関する新しい方程式によって、知識や人的資本が経済理論の中に埋め込まれ、「経済学の非物質的転回」がこの論文によって完遂された、という理解だけで、私の研究テーマには十分かと思われる。
本章において私が何より注目し関心を持ったのは、<3. マクロ経済における資本主義の「非物質化」>の項である。
何より驚いたのは著者の主張する「資本主義の非物質的転回」という現象の研究が未だ概念的・理論的論争の段階かと思っていたのであるが、それが既に膨大な実証的データの分析に基づく研究段階に入っている、という事実であった。
著者によれば、「資本主義の非物質的転回」という現象を考える上で最も注目すべきは、「無形資産」の役割の増大であり、2000年代頃から無形資産を企業会計上どのように価値評価し、位置づけるかが大きな問題になってきた、と言う。無形資産はストックとしての人的資本と、それが生み出した無形の資産からなるとされ、この生み出された無形の資産を以下のように分類できるとしている。
(1)所有権が明確で、市場での売買が可能なもの(特許、著作権、商標、ブランドなど)
(2)特定企業に所有され、コントロールすることは可能だが、企業と分離して売却することが 困難なもの(途上にある研究開発、評判・名声、独自の業務プロセスなど)
(3)企業で働く従業員やサプライヤーと企業の密接な関係の中で構築されていることから、企業によってコントロールすることが困難なもの(人に根ざした知識・スキル、コア競争力、ネットワーク、組織など)
このような無形資産の分類や認定に関しては、さらに多面的な視点からの十分な検討が必要とは思われる。しかし資本主義の将来的な動きを見極めるために重要な投資動向において21世紀に入ってからの過去20年間に無形資産の投資が顕著に増大していることに気づいた研究者がまず実証的研究に先行して取り組んだ。その先駆的実証研究はアメリカについてのコラードらの一連の研究であると言う。そして、このコラードらのアメリカを対象にした研究は、無形資産の経済的影響の推計に関する標準的手法となって各国でも応用され、国際比較研究も進んでいる、と言う。
このコラードらの研究に関して、私が最も注目したのは「現行の国民経済計算が企業による無形資産投資の重要性の高まりにもかかわらず、統計の未整備や定義の曖昧さのため、そうした傾向を統計上、十分に把握し、国民経済計算に反映させることができていない」という指摘である。これは、極めて重要な問題の指摘であり、経済学的分析研究において、そもそもその基礎になる研究調査の基礎的データが経済的実態を十分に反映していなければ、それらのデータに基づいた研究は意味をなさない。そう言う意味で、あらためて現代の経済における無形資産への支出の内容をきちんと定義し、その分類を統一的に行った上で、比較研究することが極めて重要であると思われる。
コラードらの研究では、このようなデータの基礎的整理と収集分析を行った上で、以下の結果を見出したとする。
(1)無形資産投資が1990年代を通じて急速に伸長した
(2)無形資産投資は少なくとも有形資産への企業投資と同程度の大きさだった
(3)それを反映させた経済成長率は私たちが今手にしている統計が示すものよりも高かった可能性が高い
このコラードらの研究では、無形資産は以下の3つのカテゴリーに分類されている。
(1)「情報化資産」(主として企業のコンピューターソフトウェアへの投資支出)
(2)「革新的資産」 これは、研究開発投資であるが、これは以下の2つに分類される。第一は、主として製造業や大学での科学技術に基づく技術ベースの研究開発であり、第二は、非製造業による「製品開発、デザイン、調査に関連する支出」等である。
(3)「経済的競争能力」これは企業の経営戦略の立案に関わるものであり、第一、第二のカテゴリーの無形資産投資をどのように進め、その成果をどのように活用するかを決定するための投資である。
そして、その推定金額によれば、アメリカにおける無形資産投資は時とともに増大しており、1990年代末には年間約1.2兆ドルに上り、GDPの13%以上に相当しており、1990年代の後半には、経済全体の成長率を上回るスピードで伸びていた。この結果アメリカでは1990年代後半には有形資産投資を逆転し、以後、両者の格差はさらに拡大していることが分かった。
様々な国際比較研究によれば、このような現象は、アメリカに特殊的な動きではなく、OECD諸国に共通して見られることが明らかにされている。しかし、その進展は国によって違いがあり、最も「投資の非物質化」が進んでいるのはアメリカとイギリス、その後に北欧諸国やドイツ、そして日本となっており、大きく離れて無形資産への投資水準が低いのはイタリアやスペインなどの南欧諸国である、と言う。
日本についての分析は、コラードらの研究手法に基づいて宮川努らが詳細な研究を進めている。その推定によれば、日本においても無形資産投資は1980年以降着実に増大し、2012年で約43兆円に達している。しかし問題は2000年代以降、無形資産への投資がほぼ横ばいになり世界金融危機以降はむしろ減少にすら転じている。加えて、日本のもう一つの特徴は、無形資産投資が2000年代前半に入っても有形資産投資に及ばず、1990年代後半に無形資産投資が有形資産投資を上回ったアメリカとは対照的に「無形資産投資の停滞」が特徴的に見られる、と指摘する。
次に、著者はアメリカ、韓国、ドイツにおける調査研究の結果を元に、無形資産投資による生産性向上効果も成長促進効果も製造業の物的投資効果を上回っており、また無形資産投資を事業の中核とする産業が拡大し、産業構造転換を通じて経済全体の成長を促進する、とする。そして、日本が無形資産への投資において他の先行する諸国に遅れを取っていることが日本経済の低迷の原因となっているのではないかと推測している。
さらに、以上のような近時における無形資産投資の急速な増大という状況の中で、著者は第一に無形資産投資に焦点を当てた経済政策/産業政策が必要であるが、その実行のために「無形資産」の定義を明確にした上で、無形資産に関するミクロ経済/マクロ経済上のデータを整備し、それに対する投資動向を統計的に正確に把握する必要があると主張する。そして、この点は私にとって極めて興味関心のあるところであるが、著者によれば、もしコラードらの研究手法に基づいて無形資産投資を国民経済計算に組み込むならば、GDPは今私たちが目にしている数値より大きくなる可能性が高く、成長率も引き上げられる可能性があると言う。この点は特に重要であると思われるが、現状ではGDPをはじめとする経済統計は、私たちの経済活動の全体を捉えきれておらずGDPの規模、その成長率ともに無形資産を考慮しないために過小評価となっている可能性が高く、国民経済計算体系の本格的な改定が必要になるだろうとする。
さらに、第一章で検討したサマーズの長期停滞論やゴードンの投資機会喪失論は経済の物的世界のみを取り扱っており、非物質的世界で起きている根本的な変化を踏まえていない事に留意すべきだと言う。
そして、無形資産投資が示唆するもう一つの政策的問題は日本企業による無形資産投資の停滞をどう考えるかという点である。著者によれば、これまでの理論的・実証的研究結果から、人的資本を含む無形資産への投資は生産性を高め、産業構造の転換を通じて経済成長を高める効果を持っている。日本企業の無形資産投資の伸びが鈍った1990年代後半以降の時期は日本企業の生産性が悪化し競争優位を失っていく時期と重なっている。そこで著者は日本企業の国際競争力低下の原因は「進行しつつある資本主義の非物質化への不適合」にあるのではないか、という仮説を提示する。石油ショックや円高への対応、中国など新興国への台頭などは日本企業は従来のものづくりの延長線上でうまく問題に対処してきた。しかし資本主義の非物質化はこれまで日本企業が依拠していた競争の土台が掘り崩され、新しい競争の土台が創出される「パラダイム転換」であり、この非物質化に適合したビジネスモデルへの転換ができなかった事が今日の日本企業の競争力低下につながったのではないか、と主張する。
ところで、これは私の個人的感想であるが、自分自身の消費生活を考えてみて、かつては住宅を建築し、家具や家電製品を購入し、様々な身の回り品を購入することが消費支出の大きな部分であったが、現在では国内、海外の旅行、スポーツ観戦やコンサート・絵画鑑賞あるいはテニス、ゴルフやスポーツクラブの費用等々、モノではなく、コトに対する支出が増えていることに気づく。特に現在の若者世代の支出の中で、以前のような家電機器や自動車の購入ではなく携帯電話の通信費やネットフィリックス等の配信費用が絶対的に優先されることなどは「経済の非物質化」の象徴的現象と言えるかもしれない。
最近の日経新聞電子版に以下のような記事があった。
何しろ世界に冠たるデジタル企業であるGoogleの1000億円の投資のうち、どれ位が無形資産への投資として分類されるのであろうか?「経済の非物質化」と言う視点から改めて考えてみると興味深い。
Google CEO、日本で1000億円投資 データ拠点など整備
2022/10/7 16:55
取材に応じるグーグルのスンダー・ピチャイCEO(7日、東京都渋谷区)
米グーグルのスンダー・ピチャイ最高経営責任者(CEO)は7日、日本で2024年までに1000億円を投資する計画を明らかにした。日本初となるデータセンターの建設などに充当する。景気の減速感が強まるなか業務の効率化を加速する一方、日本を含むアジア・太平洋への投資を続けて成長を取り込む。
来日したピチャイ氏が都内で日本経済新聞とテレビ東京の単独取材に応じた。「昨年から24年までの4年間で1000億円を投資し、一部をデータセンターに充てる」と説明した。同社は海底ケーブルや人材育成への投資も含むとしている。
グーグルは千葉県内で国内初のデータセンターの建設を進め、23年に稼働を始める予定だ。消費者向けのインターネットサービスの利便性を高めるほか、ピチャイ氏は「当社のクラウドコンピューティング事業を通じて日本企業のデジタル変革を支援したい」と述べた。
新型コロナウイルスの感染が広がったことを背景にグーグルのサービスの需要が拡大し、同社の親会社である米アルファベットの業績拡大が加速した。一方、足元ではインフレなどが経営の重荷となり、22年4~6月期まで2四半期連続で減益となっている。7月には年末まで採用のペースを落とすことを決めた。
ピチャイ氏は「当社の事業は企業の広告費用との相関が強く、マクロ経済の影響を受けやすい。マクロ経済の不安定さに対応する必要がある」と述べた。23年については「採用を続ける一方、22年に比べてさらにペースが穏やかになる」と説明した。
事業ではクラウド技術を活用したゲーム配信サービス「スタディア」からの撤退を決めたほか、先端開発部門「エリア120」の縮小を決めている。機器開発・販売では6日に新型スマートフォンなどを発表する一方、ピチャイ氏は「(ノートパソコンの)ピクセルブックでは他社からいい製品が出ており、(自社開発の)計画を見直した」と明かした。
一方、人工知能(AI)などの注力部門への投資は継続する。また、地域としては「今後10年間の成長の大部分はアジア市場からもたらされる」と指摘し、多様な機能をまとめたスーパーアプリやショート動画などを具体例としてあげた。また、クラウド事業について「あらゆる分野でデジタル変革が加速し、アジアは成長機会が大きい」と指摘した。