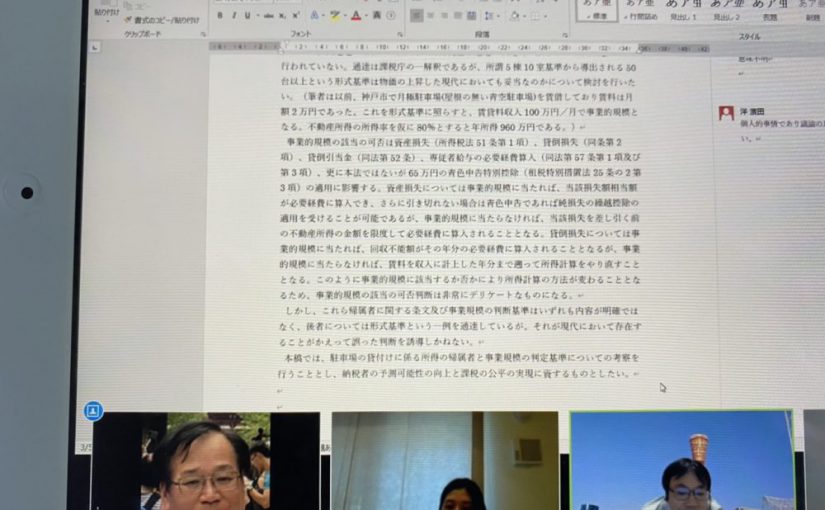昨2年間学んだ会計研究科大学院を卒業し、今春新たに同じ兵庫県立大学の経済学研究科大学院に入学したまさにその時期に、間違い無く世紀的な事件として記録されるであろう新型コロナ感染症のパンデミックが勃発しました。おかげで、新しい大学院への入学式を始めとする様々な行事は吹っ飛んでしまい、それどころか大学のキャンパスへの立ち入りすら、5月末の今も認められていない状況です。
このパンデミックに対する社会的対応策としては、ワクチンや治療薬が提供されるまでの時期は、基本的に人と人の接触を減らす事以外にはなく、あらゆる社会的活動において、人の移動と直接的接触を避けつつコミュニケーションを取る手段として、インターネット上でのオンラインシステムの活用が究極の代替システムとして、世界的に爆発的に使われる状況が現出しました。この状況自体が極めて大きなエポックメーキングな現象ですが、その事については、稿を改める事にします。
ともあれ、2か月以上が経過して、ようやく定着し始めたオンライン講義システムの中で、今度の大学院研究科の専攻である『租税法』についての初の課題レポートをまとめました。
まとめ終えて改めて考えてみると、文中の青字部分は、まさに私が会計や税務と関わりを持ち始めた原体験とも言うべきものであり、下線部の思いが、現在の大学院生活につながるものである事に気づいて、深い感慨を覚えるところです。
以下、やや専門的細部にわたりますが、転載してみます。青字部や下線部だけでも、ご一読いただければ幸いです。
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
《租税法Ⅰ》
報告日:2020年5月23日
EM20R802 松賀正考
事業所得計算における実額経費計算と概算経費計算
『大系租税法 第2版』207~276貢
〈 目次 〉
1 所得の種類による計算法
2 事業所得の計算方法
2.1 事業所得計算方法における実額控除と例外的概算控除
2.2 社会保険診療報酬の特例を巡る問題(裁判例)
① 事実の概要
② 本裁判の争点と問題点
2.3 実経験から考える
3. 参考文献
1. 所得の種類による計算方法
我が国の税制では、個人の所得は、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得、雑所得の10種類に分類されており、各所得によってその計算方法は異なる。その計算方法のパターンは大まかに言って、1)経済活動に伴う収益である益金とその収益を得るためにかかった費用である損金との差額から計算するもの、2)益金の総額に対応して一定の概算控除額を引いた差額から計算するもの、3)その他、とに分類されるであろう。
前者の1)の代表的な所得は、事業所得であり、不動産所得や山林所得譲渡所得などがこのパターンに属すると思われる。これに対して、2)のパターンの代表的なものは、給与所得や退職所得であり、これらの所得では、得られた益金の額が決まれば、一定の計算方式によって算出される控除額が決まり、その差額から所得額が計算される。すなわち、事業所得においては、益金から各種の経費が損金として差し引かれる実額経費制であり、損金としてどの範囲の経費がどの程度認められるかによって所得額が変動する。一方、給与所得等では、益金から差し引かれる経費は、一定の計算式による概算経費制であり、実際にかかった経費は所得額の計算において直接影響しない。このことが、サラリーマン等の給与所得が事業所得に比べて不公平であるという主張がなされ争われた代表的ケースが大島訴訟等である。現在では、一定の条件を満たした経費に関しては、『特定支出』として認められるようになっているが、これは、あくまで特殊なものにとどまり、実際の例においてもそれほど多くはないようである。給与所得の計算における概算経費としての給与所得控除計算や源泉徴収と年末調整などの制度は、給与を支払う事業経営者にとっては、かなりの事務的負担であるが、その事は逆に課税庁側にとっては大きな事務的負担の軽減になっているのが事実であろう。米国などの諸外国の税制においては給与所得の計算においても実額経費制が認められ、サラリーマンも自己申告によっている例もあり、各種所得間の捕捉率の差等から給与所得者の不公平感や不満は依然として大きい面があるが、課税庁側からは巨大な事務的負担の問題があり、実務上の実現は難しいと思われる。
事業所得は給与所得との区分だけではなく、譲渡所得や雑所得、時には、不動産所得や山林所得との区分においても紛らわしい場合があり、様々な議論や訴訟で問題にされる場合がある。
2. 事業所得の計算方法
2.1 事業所得計算方法における実額控除と例外的概算控除
事業所得の計算方法は、上述のように基本的に総収入金額から必要経費を控除するものとされる(所得税法27条2項)。この必要経費については所得税法37条に一般規定がある。
事業所得は必要経費の実額控除が認められ、これに対して給与所得は概算経費である点が大きく異なる。
ところが大きな例外として、社会保険診療報酬の計算方法は特例(租特26条)が認められている。すなわち社会保険診療報酬を受け取る納税者に、所得に従って57~72%で一定の概算控除選択の余地が認められている。これは社会政策上の配慮に基づく面の強いものであって同じ概算控除とはいえ給与所得における給与所得控除と比べて概算控除率が高く、いわゆる医師優遇税制と見られる面が大きい。
しかしながら同じ事業所得の計算において実額控除方式と概算控除方式が混在することによって、様々な問題や議論が発生し、時には訴訟問題となるケースもあった。
2.2 社会保険診療報酬の特例を巡る問題(裁判例)
更正処分等取消請求事件
最高裁判所昭和六三年(行ツ)第一五二号
平成二年六月五日第三小法廷判決
① 事実の概要
歯科医には自由診療が広く認められている。自由診療は実額経費計算である。歯科医が自由診療は実額経費で計算し、社会保険診療を特例で計算したが、両者の割り振りを間違えた。特措法に従って計算するより、実額で計算する方が有利であることに後で気がついたので、国税通則法19条に従って修正申告を行った。自由診療の割り振りをやり直し、両者ともに実額で計算しようとしたのであるが、税務署は更正の請求を認めなかった。
本件の訴訟の福岡地裁の第一審では、原告である歯科医の主張を認めたが、これを不服として税務署が控訴し、福岡地裁での控訴審では一転して税務署の主張が認められ、第一審の原判決が棄却された。しかし最高裁での判決は再度逆転して、第一審の原告である歯科医の主張が認められる判決となった。
② 本裁判の争点と問題点
本裁判で争われたのは、所得税の計算を行う際、複数の計算方法がある場合、申告後その計算方法を改めて修正申告をすることが税法上可能か、という点である。しかし、そもそも所得税計算をする際に複数の計算方法がある事自体に問題の出発点があるのかもしれない。いずれにしても、複数の計算方法が存在し、その計算方法の選択において、明示的に禁じられていないのであれば、課税要件明確主義から、その方法については、納税者が自由に選択できるのは当然と言えるであろう。本件に対する最高裁の判決はその立場であると思われる。
2.3実経験から考える
上述の裁判例でもあったように、事業所得の計算において、実額経費の計算によるという原則に対して、社会保険診療報酬に限り、特例的に概算経費による計算方法が認められており、両者が混在する場合、複数の計算結果が導かれる可能性があるという問題が起こりえる。
実経験に基づいて、検討してみたい。
歯科医師Xは昭和52年、明石市にて歯科医院を開業したが、その開業前に、三重県にて病気のため診療できなくなった歯科医師Yの診療所を代理医師として手伝っていた。明石での開業後も引き続き、その三重県の診療所の運営の委託を受けたXは、Yの名義の診療所に後輩の歯科医師Zを招いて、その診療実務を委託し、医院の管理運営はXが行うこととした。この診療所の名義はY医師であり保険診療報酬もYの名義で受取り、これをXはそのまま預かって、Zの給料を含む診療所運営に関わる諸経費を支払うこととし、診療所の建物、診療機材一式の使用料として毎月一定額をYに支払うという契約をした。
この年、Xは、明石市の新設医院での保険診療報酬に関しては、特措法が適用される形の概算経費控除で所得計算し、Yから委託を受けた診療所での保険診療報酬は、Y名義で受け取るものであるので、いわゆる優遇税制の適用は受けられないであろうと考え、これを保険外診療報酬、つまり自由診療報酬として実額経費計算をして、二つの診療所に関わる診療報酬による所得を合算して、申告を行った。ところが意外なことに、この申告に対して、所轄税務署から連絡があり、Yから委託された診療所での保険診療報酬についても概算経費で計算をして、二つの診療所での保険診療報酬を合算して所得計算をして修正申告をするように、との連絡が税理士を通じて伝えられた。
数字的実態を言えば、Yから委託された診療所に関わる計算では、Z医師にかなりの額の給料を支払う事情もあり、実額経費計算では経費の額が大きく、保険診療報酬が1300万円程度あったが、収支としては、140万円ほどの赤字であった(1〜3月の残務整理の3カ月のみ)。一方、明石の診療所に関しては、4800万円余りの保険収入と670万円程度の自費収入との合計5500万円程の収入に対し、実額経費計算では、3500万円程度の収支差額になるところが、特別措置法による計算では、1900万円程度に圧縮され、さらに三重県の診療所の赤字は当然、同じ事業所得内で損益通算されるので、収支差額は1800万円程度になった。
これに対し、税務署からの指摘通りに、Yから委託を受けた三重県の保険診療報酬も特措法による計算をすれば、実態は赤字であるにも関わらず、その診療報酬の額から自動的に計算される所得になるわけであるから、赤字の損益通算どころか、両方の診療所の保険診療報酬を合算して算出される所得の額は極めて大きくなり、その結果の増差税額は、246万円余りとなる状態であった。
問題のポイントは、別のY医師の名義で受け取る社会保険診療報酬をXが収入として受け取った時点で、それは本来の社会保険診療報酬とは考えられず、税務上の一種の優遇税制の対象から外れるのではないか、という事である。一時は訴訟も考えたが、税務当局とのやり取りの中で、担当税理士が申告書の記載欄に特措法適用条文を記載忘れしていたという初歩的ミスが発覚し、厳密に言えば、二つの診療所の収入の全てを実額計算せざるを得ないという事が分かり、心ならずも断念し、税務署の指示方針に従うことになった。
しかしながら、特措法の特例適用の対象となる収入は極めて厳密に限定されており、例えば、TKC税務研究所が提供する税務Q&A(文献番号 46100728)には以下の記載がある。
【質問】社会保険診療報酬の所得計算の特例適用の対象となる収入にはどのようなものがあるか。
【回答】社会保険診療報酬の所得計算の特例の適用の対象となる収入は、租税特別措置法第26条第2項に掲げる法律に基づく診療収入に限られる。
このように、特例措置の適用について極めて厳格な扱いが求められているにも関わらず、その扱いを外して一般的な実額経費計算をすることが、このケースのように結果的に所得の圧縮につながるとなれば、逆に、この特例措置を適用することを強引に求めるという姿勢は、今から振り返っても、行政上、あまりに恣意的な対応ではないかと感じられる。
今回上記に取り上げた判例の結論として「複数の計算方法が存在し、その計算方法の選択において、明示的に禁じられていないのであれば、課税要件明確主義から、その方法については、納税者が自由に選択できるのは当然」という解釈が正しいのであれば、この事例での所轄税務署の指示には疑問が残る。開業間もない時期のこのような経験は、やはり税務処理について人任せであってはならないとの思いを深く持たされたし、会計処理や税務問題への関心の出発点になったものである。
3. 参考文献
池本征男『所得税法 理論と計算』税務経理協会
佐藤英明 スタンダード所得税法 弘文堂
奥谷健「事業所得と給与所得の区分」『租税判例百選(第6版)』有斐閣72-73貢
水野忠恒『大系租税法(第2版)』中央経済社
TKC税務研究所データベース 税務Q&A(文献番号 46100728)